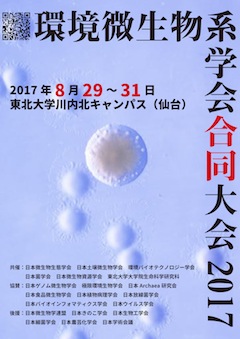プログラム
シンポジウムのプログラムはこちらになります (PDFファイル)。
企画シンポジウム
S01: ゲノムシークエンス技術・方法論の発展はどのように環境系微生物学分野の未来を変えていくのか?
次世代シーケンシングをはじめとしたゲノム解析技術およびその活用のためのバイオインフォマティクスの最新情報を展望するとともに、それらの技術の活用によって環境系微生物学の未来はどのように変わっていくのかについて、土壌微生物学分野と食品微生物学分野の例をもとに議論する。
開催:8月31日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『PacBioを用いたバクテリアのメチローム解析』古田芳一(北海道大学・人獣共通感染症リサーチセンター)
2.『我々の生活と携帯型DNAシーケンサー』丸山史人(京大・院医)
3.『土壌層位形成過程や土壌団粒構造の微生物群集構造解析』西澤智康(茨城大学農学部)
4.『次世代DNAシークエンサーの活用が食品微生物学分野にもたらしているインパクトとさらなる未来予測』木村凡(東京海洋大・院・食品生産)
5. パネルディスカッション
企画学会
日本食品微生物学会 木村凡(東京海洋大)、日本ゲノム微生物学会、日本土壌微生物学会、日本バイオインフォマティクス学会
S02: データベース・カルチャーコレクションの活用が切り開く「複眼的」環境微生物研究
データベース・カルチャーコレクションは、環境微生物研究におけるインフラであるとともに、個別研究に複眼的な視野を加えていくための鍵である。ゲノム・メタゲノム情報をはじめとする膨大なデータベース上の情報や、カルチャーコレクションに保存された信頼できる微生物株をいかに活用し、研究計画を立て、俯瞰的な解析を行い、比較実験を行っていくのか?本シンポジウムでは、これらの点について、データベース・カルチャーコレクションを活用して研究を深化させた実例について取り上げるとともに、環境微生物研究を加速するためのデータベース・カルチャーコレクションの整備の今後のあり方について、議論する場としたい。
開催:8月31日 15:00-17:00
講演タイトル・講演者
1.『環境微生物研究に貢献するカルチャーコレクションのあり方』大熊盛也(理研・JCM)
2.『NBRP大腸菌・枯草菌リソースの15年とこれからの5年』仁木宏典(遺伝研・系統生物研究センター)
3.『ゲノムとパスウェイデータベースに基づくメタゲノムの機能アノテーション』五斗進(情報・システム研究機構・DBCLS)
4.『微生物統合データベース「MicrobeDB.jp」』黒川顕(遺伝研・生命情報)
5.『データベース・カルチャーコレクションでひもとく微生物の進化』岩崎渉(東京大・院理)
企画学会
日本バイオインフォマティクス学会 岩崎渉(東大)、日本微生物資源学会 高島昌子(理研)、日本ゲノム微生物学会 大島拓(奈良先端大)
S03: 次に必要な複合微生物系解析技術
環境中の微生物の多様性や機能を調べる技術の開発は大きな進展を遂げてきている。今では、環境中の雑多なゲノムDNAを 丸ごと解読したり、また生態系を構成する微生物のゲノムを一つ一つ高精度に再構築できる時代になってきている。また環境中の微生物を可視化して調べる優れ た技術も確立されてきており、環境微生物の実態に迫ることができるようになりつつある。一方で、環境微生物を研究する上で、現状技術ではなし得ないものとはなんであろうか。本シンポジウムでは、環境微生物解析における現状技術の課題と新技術開発の動向を踏まえつつ、次に求められる環境微生物解析技術について考える契機としたい。
開催:8月29日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『Omics and genome-enabled technology to understand phylogenetic-based enzyme functions』高須賀太一(北大・農)
2.『メタボロゲノミクスがもたらす腸内微生物生態系の機能理解』福田真嗣(慶大・先端生命研)
3.『16S rRNA遺伝子アンプリコン解析の弱点と最新技術』関口勇地(産総研バイオメディカル)
4.『マルチ顕微鏡活用術』野中茂紀(基生研)
5.『微生物社会を視る観察技術』尾花望(筑波大学生命環境系)
企画学会
日本微生物生態学会 尾花望(筑波大)、玉木秀幸(産総研)、日本ゲノム微生物学会 大島拓(奈良先端大)
S04:“培養”技術で紐解く生物界の暗黒物質の正体
環境ゲノム解析研究全盛の時代である。超高速シークエンサーの革命的な発展とバイオインフォマティクス技術の進展により、今では複雑な微生物生態系であっても,その構成種のゲノムを高精度に解読したり、実環境中で発現している代謝機能を推定できるなど、生物界の暗黒物質と称される未知微生物の実態にこれまで以上に深く迫ることが可能になりつつある。それでもなお、「未知の微生物を"培養"して生命の機能を探る」というアプローチが重要だと言ってくれる研究者が少なからずいる。いや、むしろ、生物界の暗黒物質の謎を紐解くには、ややもすると古典的とみなされがちな「培養して調べる」というアプローチと環境ゲノム情報解析の両輪が必要だとの認識が世界的にも広まってきている。本シンポジウムでは、培養技術と環境ゲノム解析技術のそれぞれの強みを活かした融合研究の成果や、培養しなければ決して分からない新生物機能の発見の事例、さらには系統分類学に基づいた高次分類群の設立の事例等を紹介しながら、生物界の暗黒物質の実態解明研究において、未知の微生物を活きたまま培養して解析することの意義、新たな培養技術開発の重要性や微生物系統保存の基盤を担うカルチャーコレクションの役割を再考する契機としたい。
開催:8月31日 17:00-19:00
講演タイトル・講演者
1.『未知の微生物を"培養"して生命の新機能を探る』玉木秀幸(産総研・生物プロセス)
2.『微生物暗黒物質は暗黒ではない—海底下生命圏からの未培養微生物の培養を例として—』井町寛之(JAMSTEC)
3.『極限への適応:培養と環境ゲノミクスで紐解く生命の生存戦略』鈴木志野(JAMSTEC・高知コア)
4.『すくすく育て!未培養微生物』飯野隆夫(理研BRC-JCM)
5.『分離培養の進展を阻害しているのは、「分離出来ない」って思い込み以外の何ものでもない』花田智(首都大・院生命)
企画学会
日本微生物生態学会 玉木秀幸(産総研)、井町寛之(JAMSTEC)、日本微生物資源学会 飯野隆夫(理研JCM)
S05: 微生物のサバイバルゲーム
実環境や微生物処理、微生物による発酵生産などの種々の現場では、微生物の殺し合いやフィットネスの大小による優占化、利益供与などの様々な相互作用・共生が起こっており、その結果として一部の構成種が生き残ったり機能したりする。その現象の背後には、種々のメカニズムがあるが、現場でメカニズムをとらえることは困難なことが多く、優占化・生き残りを制御することは難しい。本シンポジウムでは、これらの生存競争現象を捉え、そのメカニズムと意義を議論するものにしたい。
開催:8月31日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『殺す:薬剤耐性菌のVI型分泌機構を介した拡散機構』鈴木仁人(国立感染症研究所 薬剤耐性研究センター)
2.『出し抜く:プラスミドというハンディキャップとその乗り越え方』水口千穂(東京大・生物工学セ)
3.『逃げる:捕食者から逃避する細菌の細胞運動』諸星聖(首都大・生命)
4.『利用する:汚染物質分解コンソーシアムにおける非分解菌の役割』加藤広海(東北大・院生命)
5.『食べる:捕食の関係が作り出す水処理技術の新たな展開』羽部浩(産総研・環境管理)
企画学会
環境バイオテクノロジー学会 野尻秀昭(東大)、日本微生物生態学会 永田裕二(東北大)
S06: 共生微生物—我々の理解はどこまで進んだのか?
微生物が他の生物に「共生」する例は様々な分類群間で見られ,植物共生糸状菌への細菌の共生など,多重共生の例も多数報告されている。共生を介した重層的な生物間相互作用は,生態系,更に地球環境全体にも大きく影響することから,共生のメカニズム,また,その産業への応用まで,関連最新知見の共有と分野間の交流を図る。
開催:8月31日 15:00-17:00
講演タイトル・講演者
1.『共に生きる菌類と細菌−内生細菌は宿主菌類をどう変えるのか?−』高島勇介(東京農工大院・連合農学)
2.『昆虫共生細菌—その驚きの機能と分子メカニズム』安佛尚志(産総研・生物プロセス/CBBD-OIL)
3.『異種生物の受容を制御する機構;アーバスキュラー菌根共生を中心に』武田直也(関西学院大学・理工)
4.『機能解析から迫る根部内生菌の正体』春間俊克(筑波大学大学院・生命環境)
5.『飛ぶ鳥も落とす勢い?「エンドファイト」の産業利用の現状』菅原幸哉(農研機構 畜産研究部門)
6. 総合討論
企画学会
日本菌学会 菅原幸哉(農研機構)、日本土壌微生物学会 成澤才彦(茨城大)
S07: 環境ウイルスたちの多様な存在様態 -かつてないウイルス研究がここに集う-
ウイルスは、様々な生物の病気を引き起こしたり、微生物集団において優占種(あるいは優占株)を減少させるなど、宿主を攻撃する(死滅させる、あるいは増殖を抑える)能力を持っている。しかし近年の研究により、私たちが知るこうしたウイルスの姿は、生態系内における彼らの役割のごく一側面に過ぎないことが分かってきた。こうした背景の下、自然界でのウイルスの真の存在意義を解明するための科学研究が強く望まれている。国内でも、2016年度から新学術領域研究「ネオウイルス学(Neo-Virology)」が発足するなど、ウイルスを地球生態系の構成要素として捉え、ウイルスが生物の生命活動や生態系に及ぼす影響やその機能メカニズムを解明するための取り組みが本格的に開始されたところである。本シンポジウムでは、多様なバックグラウンドを持つ聴衆の皆様とともに、菌類に感染するマイコウイルスや植物ウイルス、水圏ウイルスなどの話題を共有し、様々な環境中におけるウイルス対宿主の関係性を巡る幾つかの新しいストーリーについて論じてみたい。
開催:8月29日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『何故に今頃ネオウイルス学?』緒方博之(京大・化研)
2.『ウイルスが宿主をトレーニングする?:知られざる菌類の生態戦略』森山裕充(東京農工大・院農)
3.『植物に潜在感染しているウイルスの役割:ウイルスは植物の生存戦略に寄与できるか?』高橋英樹(東北大学 大学院農学研究科)
4.『海洋微生物を巡るウイルス研究:寛容が拓く共存の姿』長﨑慶三(高知大学農林海洋科学部)
5.『ウイルスもまた宿を借りる:驚くべき菌類ウイルスの奸智』鈴木信弘(岡山大学 資源植物科学研究所)
企画学会
日本ウイルス学会 長崎慶三(高知大)、日本菌学会
S08: 海外遺伝資源の利用におけるカルチャーコレクションや分類学関連施設の役割
名古屋議定書の「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」を踏まえて、海外産菌株や海外産遺伝資源を用いた研究をどのように実施すべきか、その成果発表の際に留意すべき点、そして研究・開発を推進し、タイプ株の保存や遺伝子資源の保全、生息域外保全の観点からも重要な役割を担うカルチャーコレクションや博物館などの分類学関連施設が取り組むべき今後の課題等について紹介する。国内外の最新の動向やコレクション担当者及び利用者双方の視点からの意見を踏まえて、今後取り組むべき課題や整備すべき体制と制度について議論出来る場としたい。
開催:8月29日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『名古屋議定書に関する国内外の動向』中原一成(環境省自然環境局)
2.『名古屋議定書時代の研究者が考えるべき課題』森岡一(東京農業大学)
3.『海外生物資源の利用とNITEの取り組み』安藤勝彦(NITE・バイオ)
4.『分類学関係施設のABSに対する取り組み』保坂健太郎・細矢剛(国立科学博物館)
5.『カルチャーコレクションとABS対応について』伊藤隆(理研・BRC)
企画学会
日本微生物資源学会 河地正伸(環境研)、微生物生態学会
S09: あなたの常識は非常識?:RNA研究の最前線
環境微生物研究において、rRNAは分類の指標として、tRNAの同定は全ゲノム解析のルーチンワークとして(?)、多くの場合、深く考えずに解析される。研究室では、rRNAのステム構造は保存性が高い、多様性解析でrRNAのキメラ配列を検出しないといけない等、何の疑問も呈さずに議論されていることが大半であろう。しかし、生命の黎明期から機能分子として働いてきたRNAは、プロセシングや修飾、分断してコードされるtRNA、ゲノムのコード領域を探すだけでは見つからない機能性RNA等、これまでの常識に収まらない“非常識な進化”を遂げていることが、近年、明らかにされてきた。本シンポジウムでは、あなたの常識に挑戦する、知る人ぞ知るRNAの世界を紹介し、議論する。
開催:8月31日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『バクテリア16S rRNA遺伝子の進化』宮崎健太郎(産総研・生物プロセス)
2.『tRNA遺伝子の構造の多様性と進化』相馬亜希子(千葉大院・園芸)
3.『tRNA成熟化機構に見られるアーキアの生存戦略』平田章(愛媛大・院理工)
4.『mRNAの3'末端から生成する機能性RNA』宮腰昌利(秋田県大・生資科)
5. 総合討論
企画学会
極限環境生物学会・日本Archaea研究会 布浦拓郎(JAMSTEC)、日本微生物生態学会 玉木秀幸(産総研)、日本ゲノム微生物学会 大島拓(奈良先端大)
S10: 環境微生物ゲノムの見方・ポストゲノム研究
ゲノムデータはたっぷり持っているのだが、なんとなくうまく使えていない気がする。ゲノム解析をしてみたけれど、自分のやり方は間違っている気がする。相同性解析ばかりで面白くないし、直接的なエビデンスが欲しい。隣の研究者は、どう実験をデザインしているのだろう。また、どういう共同研究で壁を超えているのだろう。ポストゲノム解析に二の足を踏み、収拾がつかない解析結果を前に思い悩む研究者に向けて、ゲノム情報を使い倒した経験者から、それでいいのか!そんなこともできるのか?を喚起する様々な解析手法を紹介していただく。
開催:8月31日 17:00-19:00
講演タイトル・講演者
1.『細菌の遺伝子サイレンシング』大島拓(富山県立大・生物工)
2.『マルチオミックスを利用した機能ゲノム解析』奥田修二郎(新潟大・院医歯学)
3.『ランダム変異による超好熱アーキアのポストゲノム解析』福居俊昭(東工大・生命理工学院)
4.『原核生物で発見された真核生物型ユビキチンシステムの機能解析』金井保(京都大・院工)
5.『高精度転写解析を通してみるロイコノストックの生き様』石川周(神戸大・イノベーション)
企画学会
日本ゲノム微生物学会 大島拓(奈良先端大)、日本Archaea研究会、布浦 拓郎(JAMSTEC)、日本バイオインフォマティクス学会、日本微生物生態学会、極限環境微生物学会
S11: 微生物生態系の仕組みの理解に向けた挑戦
微生物生態系の形成・発達機構から、微生物生態系の維持・安定性や頑健性に関わる因子やその評価方法など、まだまだ分からないことだらけである。微生物生態系の仕組みの理解に向けたさまざまな取り組みが、幅広い研究領域で行われている。本シンポジウムでは、講演者の先生方に、今できることとその限界を俯瞰していただたうえで、生態系の真の姿の解明に近づくために必要な技術・戦略・理論を提言いただき、聴衆を交えて、これからの研究展開・発展について、議論したい。
開催:8月31日 15:00-17:00
講演タイトル・講演者
1.『合成生態学に期待できることとその限界 ー微生物の共存・生態系の恒常性機構を考えるー』二又裕之(静岡大学グリーン科学技術研究所)
2.『生態学理論とは何か? —微生物生態学との関係』三木健(国立台湾大学海洋研究所)
3.『集団の挙動に大きな影響を及ぼす個体の変形性』益子岳史(静岡大・工)
4.『異分野連携のためのイロハと数学者の苦悩』齋藤保久(島根大院・数理科学領域)
企画学会
微生物生態学会 春田伸(首都大)
S12: 微生物を活用した栽培技術の開発と普及
植物に対する養分供給と病害防除について、微生物を活用した技術の開発研究を行っている4名の研究者に話題提供してもらう。
開催:8月31日 17:00-19:00
講演タイトル・講演者
1.『土壌を創造する -デザイナー・ソイルの可能性-』篠原信(農研機構)
2.『世界のブドウを救え!根頭がんしゅ病の生物防除技術の開発』川口章(農研機構・西日本農研)
3.『土着菌を活かす:CDU施用により集積される微生物を用いた土壌伝染性病害の生態学的防除の可能性』横山和平(山口大・院創成科学)
4.『バチルスバイオ肥料「きくいち」の特性と水稲栽培体系への導入』横山正(東京農工大学 大学院農学研究院)
企画学会
日本土壌微生物学会 齋藤明広(静岡理工科大)、門馬法明(園芸植物育種研究所)、日本植物病理学会
公募シンポジウム
公募シンポジウム1:「電気を創る微生物」と「電気を食べる微生物」
近年、微生物と鉱物(電極)、あるいは異種微生物間での直接的な電子移動(細胞外電子移動)を利用してエネルギーを獲得する微生物(いわゆる電気を創る微生物、電気を食べる微生物)が相次いで発見されている。これらの微生物は学術的にも非常に興味深い研究対象であるとともに、微生物による電力生産(微生物燃料電池)や、微生物への電子注入による物質生産、金属腐食の制御等、様々な有用技術への応用可能性を秘めており、新たなバイオプロセス開発のブレイクスルーとなると期待される。しかし当該分野の国内研究者数は海外に比べまだ少なく、今後さらなる普及と進展が望まれる。そこで環境バイオテクノロジー学会と微生物電気化学研究部会(微生物生態学会内)では、異分野研究者間の知識共有と共同研究の機会創出を目的とし、本シンポジウムを合同で企画した。本シンポジウムでは「電気を創る微生物」と「電気を食べる微生物」について、その生態系、電子移動のメカニズム、およびその応用技術(微生物燃料電池、微生物電気合成、金属腐食制御)について、国内研究者による最先端の研究を紹介する。本企画は微生物生態学と環境バイオテクノロジーの融合という点で本合同大会の趣旨に合致するものであり、国内の当該分野研究の活性化に大きく貢献できると期待される。
開催:8月31日 17:00-19:00
講演タイトル・講演者
1.『微生物電気化学の概観と展望』井上謙吾(宮崎大・農)
2.『システムゲノミクスで解き明かす“発電微生物”の多様な生き様』石井俊一(JAMSTEC・海底資源研究開発センター)
3.『電気による微生物の代謝制御と物質生産』高妻篤史(東京薬科大・生命)
4.『金属中の電子を抜き出して食べる微生物達』若井暁(神戸大院・イノベ)
5.『微生物による腐食と電気化学的現象』伊藤公夫(新日鐵住金・先端研)
オーガナイザー
井上謙吾(宮崎大)、高妻篤史(東京薬科大)、石井俊一(JAMSTEC)
公募シンポジウム2:微生物の元素戦略:ちょっと変わった元素を使う微生物とその利用可能性
本企画は「普通の生物が使わない変わった元素を使う微生物がいたら面白いよね、なんか役に立ちそうだよね」という素朴なアイディアにもとづいている。タイトルにある「元素戦略」とは、希少元素や有害元素の使用を控えた機能材料の開発を目的とし、2012年度より文部科学省が実施しているプロジェクトの名称である。この中には光合成活性中心を模倣したMnベースの水酸化触媒の開発など、いわゆるバイオミメティクス的な技術開発も多く含まれている。しかしそもそも我々は生物、特に系統的・生態的に多様な微生物が有している元素利用のポテンシャル、いわば「微生物の元素戦略」を理解しきれているのであろうか?生物は主要な構成元素としてH、C、N、O、P、Sを、主要な陽・陰イオンとしてNa、Mg、K、Ca、Clを、さらに必須微量元素としてFe、Mn、Niなど10種程度の金属元素を利用するとされている。すなわち、地球上で確認されている100を超える元素種のうち、一般的な生物が利用しているのはわずか二十数種にすぎない、と言える。残りの約80もの元素は生物に全く利用されていないのであろうか?答えは単純にノーであり、一部の微生物は「普通ではない」元素の利用能を持ち、おそらくはそれにより競争的な優位性を得ているのである。本シンポジウムでは、日本を代表する「変わった元素を利用する微生物の研究者」たちから、微生物の元素戦略研究の最先端をご紹介いただく。
開催:8月31日 15:00-17:00
講演タイトル・講演者
1.『貴金属(Au, Pd, Pt, Rh)を取り込み金属ナノ粒子を産出する微生物』小西康裕(大阪府大・院工)
2.『植物共生細菌によるレアアース元素の利用 —新奇なレアアース依存型メタノール代謝系—』中川智行(岐阜大・応用生物)
3.『微生物によるヨウ素(I)の利用』天知誠吾(千葉大院・園芸)
4.『ケイ素(Si)で胞子をコーティングするBacillus属細菌』池田丈(広島大・先端物質)
5.『セシウム(Cs)を取り込む微生物』加藤創一郎(産総研・生物プロセス)
オーガナイザー
加藤創一郎(産総研)
公募シンポジウム3:大気と宇宙微生物生態学の幕開け
大気圏上空での微生物に関しては、その場所への接近の困難さから限られた研究しか行われていなかった。1930年代から飛行機や大気球、気象観測ロケットを用いた微生物採集実験がおこなわれてきた。しかし、上空での微生物密度が低いため、つねに地上微生物の混入が問題となった。大野らは、その可能性を極力低減した採集を実施し、微生物採集に成功した。これまでの歴史と最新の結果を報告する。国際宇宙ステーション内部(予圧部)では宇宙飛行士が居住しているため、その衛生管理上からも微生物モニタリングが重要となっている。日本実験棟での継続的モニタリング結果を那須と槇村が報告する。国際宇宙ステーションの外部はほぼ真空状態であり、そもそも微生物が存在するかどうかが大きな問題であるが、もしそこに微生物が存在すれば、地球微生物の宇宙への移動可能性の検証となる。その最初の試料の解析が進行しており、その結果を河口が報告する。火星探査によって火星に微生物の存在の可能性が高まってきた。日本の研究者によって蛍光色素を用いた探査装置の開発が進んでいる。その現状を吉村が報告する。日本での研究者組織が比較的小さく、異分野研究者が遭遇する機会が比較的大きいことから、この分野の研究で日本は先端を走っている。この分野を牽引する研究者の研究を通して、研究の現状と今後の可能性に関して議論する。さらに多くの研究者のこの分野への参入を期待する。
開催:8月31日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『Biopauseプロジェクト:大気球を用いた成層圏微生物採取実験』大野宗祐(千葉工業大学惑星探査研究センター)
2.『国際宇宙ステーション与圧部の微生物モニタリングと群集構造 ---宇宙居住と地上応用---』那須正夫(大阪大谷大・薬)
3.『国際宇宙ステーション予圧部の真菌群集とそのインパクト』槇村浩一(帝京大・医共教研)
4.『国際宇宙ステーション曝露部での微生物宇宙生存機構解析と採集実験』河口優子(東京薬科大学・生命科学 )
5.『火星での「微生物」生存可能性と蛍光顕微鏡を用いた探査技術開発』吉村義隆(玉川大・農)
オーガナイザー
山岸明彦(東京薬科大)、高井研(JAMSTEC)
公募シンポジウム4:バクテリアのオルガネラ?!: 特殊な構造体がもたらす細菌のユニークな生存戦略
最新版の”Molecular Biology of the Cell”にも、”Unlike a bacterium, a eukaryotic cell is elaborately subdivided into functionally distinct, membrane-enclosed compartments.”という記述があり、オルガネラは真核細胞特有の細胞内区画であると考えられてきた。しかしながら、シアノバクテリアのカルボキシソームのようにタンパク質で構成されている細胞内区画は原核生物でも古くから知られている。リン脂質膜で囲まれた構造体においても磁性細菌のマグネトソーム、アナモックス細菌のアナモキソソーム、紅色細菌のクロマトフォアなど続々と発見されている。これらの構造体はそれぞれの細胞内で特化した機能を有しており、オルガネラと呼ぶべきものである。さて、原核・真核における違いを考えてみると、真核生物では共通したオルガネラが普遍的に存在するのに対し、原核生物ではそれぞれの種で異なるオルガネラが存在しており、細菌独自の機能発揮に寄与している。本シンポジウムでは、環境微生物分野から発信される細菌オルガネラの新しい魅力に迫るとともに、オルガネラ形成により生み出される生存戦略について議論したい。
開催:8月31日 15:00-17:00
講演タイトル・講演者
1.『磁石を作るオルガネラ:磁性細菌の磁気コンパス』田岡東(金沢大・理工・自然システム)
2.『オルガネラ?細胞小器官?:光合成を担うチラコイド』粟井光一郎(静岡大・院理学)
3.『低栄養条件で作られるオルガネラ:オリゴボディー』吉田信行(静大院・総合科技)
4.『ヒドラジンを合成するオルガネラ:嫌気性アンモニウム酸化細菌のアナモキソソーム』押木守(長岡高専・環境都市)
5.『中身のないオルガネラ:ガス小胞形成細菌の浮浪とfloat』田代陽介(静大院・総合科技)
オーガナイザー
田代陽介(静岡大)、吉田信行(静岡大)
公募シンポジウム5:微生物を使った「ものづくり」最前線 〜代謝物から酵素まで〜
バイオプロセス産業における微生物酵素および抗生物質をはじめとする微生物由来代謝物が人類にもたらした恩恵は計り知れない。近年の微生物ゲノムの大規模解読により、微生物の「ものづくり」へ対する潜在能力は我々の想定以上に高いことが明らかになった。環境調和型社会を見据えた今後を鑑みると、微生物資源に基づいた「ものづくり」はますます重要になってくると思われる。そこで本シンポジウムではこれら微生物を用いた「ものづくり」の産学交えた成果を紹介する。共生関係を利用した放線菌の抗生物質生産活性化や微生物代謝を模倣した人工生合成系の創製、微生物を用いたバイオポリマー生産の実用化、腸管炎症を抑える機能性脂肪酸生産の確立、微生物由来リパーゼを利用したバイオプロセスなど、微生物由来ものづくりを幅広く紹介したい。
開催:8月31日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『複合培養を利用した放線菌二次代謝活性化機構の解析と新規抗生物質探索』尾仲宏康(東京大・院農生科)
2.『人工生合成系を活用した擬天然物の創製戦略』後藤佑樹(東京大学・院理)
3.『天然型高分子「PHBH」発酵生産技術の開発と実用化』佐藤俊輔(株式会社カネカ)
3.『ポストバイオティクスを活用した機能性脂肪酸HYAの実用化開発』米島靖記(日東薬品工業株式会社)
5.『微生物由来リパーゼの開発』小池田聡(天野エンザイム株式会社)
オーガナイザー
尾仲宏康(東大)
公募シンポジウム6:硫黄循環に寄与する微生物と硫黄化合物が持つ新規な機能
本シンポジウムでは、生物地球化学サイクルのうちで、生命活動にも必須な「硫黄」の循環に着目する。微生物、高等植物は土壌中の無機硫黄(主に硫酸塩)を取り込み有機性硫黄化合物に固定する硫黄同化系が存在する一方、ヒトを含めた哺乳類には、この硫黄同化経路は存在しない。そのため哺乳類は生命活動の維持に必要な硫黄源を微生物・植物に依存しており、微生物・植物による有機性硫黄への固定と哺乳類による無機性硫黄への異化という一方向に循環すると考えられる。大気中の無機性硫黄化合物の発生や微生物による利用の可能性などについて最初に紹介する。次に、キノコなどの菌類や一部の細菌のみが合成できるエルゴチオネインの生産と役割、さらに植物が放出するメタノールを利用することで植物表面に広く存在し、その接種により植物の成長が促進される微生物について、そのメカニズムについて最新の情報を紹介する。微生物の培養と同様に植物栽培系で重要視されてこなかった栄養源としての「硫黄(代謝)」の生物化学的循環をテーマとして、大気中の硫黄を利用した有用物質生産の可能性や微生物と植物の相互作用による土壌フローラへの影響など、きわめて重要な機能に結びつくユニークな生理活性物質としての「硫黄」について、会場の皆さんと議論できる場を創りたい。
開催:8月31日 17:00-19:00
講演タイトル・講演者
1.『大気中の硫化物の発生と分解の新規プロセス』片山葉子(農工大・院農学)
2.『放線菌におけるエルゴチオネイン生産とその役割』佐藤康治(北大・院工)
3.『植物共生メタノール資化性細菌Methylobacterium属細菌におけるエルゴチオネイン生産と役割』谷明生(岡山大学資源植物科学研究所)
4.『生物間移行するユニークな硫黄化合物と食との関係』大津厳生(筑波大学高細精医療イノベーション研究コア)
オーガナイザー
片山葉子(農工大)
公募シンポジウム7:土壌微生物を起点とする微生物生態研究の新展開:目からウロコの新発見
土壌は最も多様性豊かな微生物叢、すなわち最も多様な微生物の生き様が混在する環境であり、何時の時代も微生物生態学者を魅了してやまない研究対象である。一方で、複雑さや不均一さといった高いカオス性を帯びているため、土壌微生物の世界は理解し難いものと考える研究者も少なくない。しかしながら、陸域の物質循環や高等生物との相互作用を切り口として、土壌微生物の生態解明は着実に進捗している。その中にはこれまでの微生物生態の既成概念を覆す新知見も報告されており、陸域生態系における微生物の重要性をますます高めるとともに、基礎科学の領域を超えて環境保全・食料生産といった喫緊の人類的課題の克服に資する知見も見出されている。本シンポジウムでは、土壌微生物学ひいては微生物生態学のマイルストーンとなりうる「目からウロコな」新発見に至ったシンポジストの講演を通して、どのようなアプローチや着眼点で微生物生態学の新発見を生み出していくのかプログレッシブな議論を深める契機を提供する。
開催:8月29日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『酸性土壌の窒素循環のミッシングリンクを解く:耐酸性新属アンモニア酸化細菌の分離・特徴・機能』早津雅仁(農研機構・農業環境変動研究センター)
2.『水田土壌の鉄還元菌のもう一つの顔:窒素肥沃度を支えるキープレーヤー』増田曜子(東京大・院農)
3.『内生糸状菌とシロイヌナズナのリン栄養依存的な共棲関係の理解及びその効果の強化に向けて』晝間敬(奈良先端大)
4.『菌根共生による植物耐酸性の限界突破...そんなに単純じゃない:第三のプレーヤー候補マイコウィルス』江沢辰広(北海道大・院農学)
5.『土壌微生物と昆虫間にあるHidden greats:土壌微生物が害虫カメムシを育む』伊藤英臣(産総研・生物プロセス)
オーガナイザー
妹尾啓史(東大)
公募シンポジウム8:自然環境下に生息する病原体を探る
自然環境中には、土壌や環境水、動物など様々な場所に微生物が存在する。ヒトに感染症を引き起こす細菌(病原細菌)も例外ではなく、環境から直接的に、あるいはその自然宿主(リザーバー)となる動物や食品を介してヒトの体内へ侵入し、病原性を発揮することがある。ペストとネズミ、リケッチアとダニ類、腸管出血性大腸菌とウシ、あるいはカンピロバクターとトリのように、主要なリザーバーが明らかにされているケースもあるが、自然環境に浸淫する病原細菌には、感染経路や生態学的知見について不明な点が数多く残されている。本シンポジウムでは、そうした病原細菌が原因となる感染症に対する公衆衛生学的アプローチ、すなわち危険要因の探索や発生の予防という観点に立ち、起因菌の分離・同定および分離株の解析を実施している4名の演者にその研究成果を紹介いただく。各演題を通して、細菌の生存戦略として病原性を捉え、病原細菌の多彩なふるまいを俯瞰できる場としたい。
開催:8月29日 13:00-15:00
講演タイトル・講演者
1.『抗酸菌属における病原性とその動物症例』和田崇之(長崎大・熱研・国際保健)
2.『レジオネラ属菌の生活環境における分布状況と遺伝学的特徴』中西典子(神戸市環境保健研究所・感染症部)
3.『つつが虫病の謎に迫る』瀬戸順次(山形衛研・微生物)
4.『食品製造環境から分離されるリステリアの特徴と施設定着要因の考察』中村寛海(大阪健安研・微生物課)
オーガナイザー
和田崇之(長崎大)
特別企画
AMED特別企画:HFSPグラントへの招待
ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)は生体の精妙かつ複雑なメカニズムに焦点を当てた革新的、学際的、かつ新規性を備えた基礎研究を支援する国際グラントです。研究対象は、分子や細胞レベルにおける生物機能から、高次の神経基盤における複雑な生物システム、さらには生態系における生物相互作用にまで及びます。特に、ライフサイエンス以外の分野(物理学、数学、化学、情報科学、工学等)の科学者達の専門知識を活用した、独創的な最先端の共同研究に大きな重点を置いています。本特別企画では、審査委員経験者や若手研究グラントの受賞者をお招きし、国際・学際的共同研究の魅力やプロポーザル作成にあたって留意すべき事項についての重要なポイントをお話して頂きます。
開催:8月29日 18:00-19:35
タイトル・話題提供者
1.『ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム(HFSP)の紹介』古川修平(日本医療研究開発機構 / AMED)
2.『HFSPグラントの審査過程とポイント』金城政孝(北海道大学 大学院先端生命科学研究院)
3.『制限酵素修飾系の進化に関するHFSP国際共同研究を終えての所感』若本祐一(2011年若手研究グラント受賞者、東京大・院総合文化)
4.『How to prepare HFSP grant proposal』宮崎亮(2016年若手研究グラント受賞者、産総研・生物プロセス)
企画責任者
宮崎亮(産総研)
シンポジウムの企画の募集について
公募シンポジウムの募集を締め切りました。たくさんのご応募をありがとうございました。
環境微生物系学会合同大会では企画シンポジウムに加えて、公募シンポジウムの企画を募集します。企画シンポジウムとは趣の異なった、ユニークかつ旬なトピックを扱ったシンポジウムをお待ちしておりますので、どうぞ奮ってご応募ください。(pdfはこちら)
公募シンポジウム
時間:110分(準備・休憩時間も含めて)
使用会場:200-400人の会場を準備しております。
採用件数:4件
応募資格:企画責任者(オーガナイザー)または共同オーガナイザーの1名は、共催学会(日本微生物生態学会、日本土壌微生物学会、環境バイオテクノロジー学会、日本菌学会、日本微生物資源学会)および協賛学会(日本ゲノム微生物学会、極限環境生物学会、日本Archaea研究会、日本食品微生物学会、日本植物病理学会、日本放線菌学会、日本バイオインフォマティクス学会、日本ウイルス学会)のいずれかの学会員であることが必須です。
締め切り:2017年4月10日
採択:応募いただいた企画案の採否は大会実行委員会において決定し、その結果を4月14日前後までに応募者へご連絡いたします。
※採択日程を早めました。
応募方法
以下の内容を記載し、件名「環境微生物系学会合同大会 シンポ企画の応募」としたメールを、下記アドレスへ送付して下さい。
1. 企画責任者(オーガナイザー)の氏名、所属、連絡先(メールアドレス、電話番号)
2. 共同オーガナイザーの氏名、所属、連絡先(メールアドレス、電話番号)
3. シンポジウムのタイトル(仮タイトルでも可)
4. 企画趣旨と概要(600字以内)
5. 予定講演のタイトル(仮タイトルでも可)、講演者氏名、所属
6. 200-400人の会場を準備しておりますので、想定参加人数をお知らせください。
応募先、および問合せ先
katee * ige.tohoku.ac.jp (*を@に変えてください)
合同大会実行委員会 公募シンポジウム担当 加藤広海(東北大 生命科学研究科)